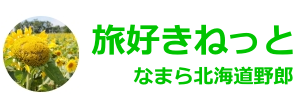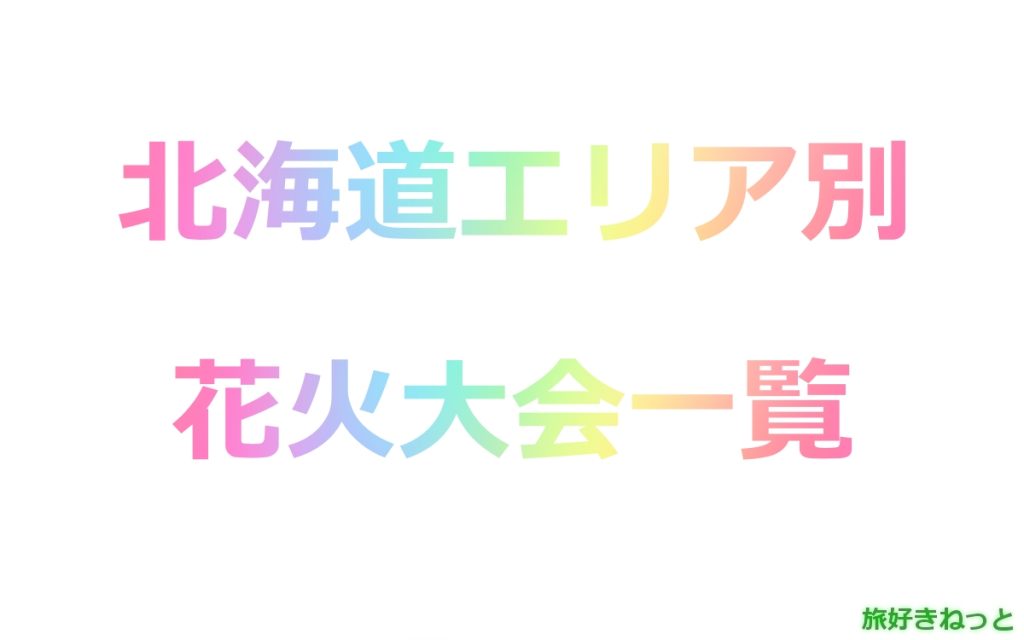苫小牧にある緑ヶ丘公園(金太郎の池)で紅葉撮影をしてきました。
10月25日に行きましたが、丁度、紅葉の見頃時期で、色鮮やかな紅葉を見ることができました。
紅葉がメインでしたが、金太郎の池には、鯉やカモ・オオセグロカモメなどの水鳥、熊目撃情報があり、高丘森林公園は立入禁止でしたが、入口付近で野生の鹿が見れたりと、桜や紅葉の季節以外でも、動物撮影が楽しめる公園です。
ここでは、緑ヶ丘公園(金太郎の池)の遊歩道(950m)を3周しながら撮影した秋の風景写真を載せています。
緑ヶ丘公園(金太郎の池)の遊歩道を歩きながら撮影した秋の風景

南側にある緑ヶ丘公園(金太郎の池)の駐車場側から撮影した、緑ヶ丘公園(金太郎の池)の紅葉です。12時頃に到着したのですが、最初は曇っていました。しかし、金太郎の池の遊歩道(950m)を1周終えた頃に天気が良くなり撮影を再開することにしました。この写真は、曇っていた時に撮影した写真になります。

北側にある緑ヶ丘公園(金太郎の池)の東側には、レストハウス(利用料無料のバーベキューコーナー)や、遊具、ローラー滑り台、トイレ、自動販売機があります。

緑ヶ丘公園(金太郎の池)には、たくさんのカモが泳いでいました。
ボート乗り場(管理人事務所)もあり、30分200円で手漕ぎボートを利用できます。

紅葉の見頃時期に手漕ぎボートに乗ると、とても綺麗な風景を見ることができますね。北海道の夏も暑いので、涼しい季節に手漕ぎボートに乗るのが良さそうです。

緑ヶ丘公園(金太郎の池)に生息するカモが、手漕ぎボートに近寄ってくるのも可愛いです。

金太郎の池に張り出した観覧デッキからは、水鳥の他に鯉も観察できます。

緑ヶ丘公園(金太郎の池)には、巨大な鯉が生息しています。
本来、公園などの池には黒色系の真鯉のみが生息しているはずですが、金太郎の池には、白・赤(丹頂紅白)・オレンジ黄金などの品種改良された錦鯉が泳いでいて驚きました。しかも、その錦鯉はどれも巨大でした。

観覧デッキの柵に、オオセグロカモメが何度も止まっていました。人慣れもしています。

緑ヶ丘公園(金太郎の池)西側の紅葉写真です。色鮮やかで綺麗でした。

緑ヶ丘公園(金太郎の池)の四阿(東屋)から、東にあるレストハウス側の紅葉写真です。

金太郎の池の四阿(東屋)に行く橋上からも、レストハウス側の紅葉写真を撮影しました。


緑ヶ丘公園(金太郎の池)のトイレは、入口付近(レストハウスの隣)と、東側の遊歩道を歩いて北側に行くとトイレがあります。

緑ヶ丘公園(金太郎の池)の遊具広場(ちびっこ冒険広場)です。

全長102m、高低差約20mのローラー滑り台が大人気のようでした。

ローラー滑り台は、階段を上った山のてっぺんがスタートになります。

緑ヶ丘公園(金太郎の池)の遊歩道は1週950mあるのですが、気付けば3周もしていました。ここの遊歩道では、犬の散歩や、ランニング目的で来ている人もいます。
確かに良い運動になりますね。

西側の紅葉写真。先程の写真よりも遊歩道を北側に歩いて撮った写真です。フルサイズカメラ、焦点距離:15mmのレンズで撮影しました。

遊歩道を北側に歩いて行くと、緑ヶ丘公園(金太郎の池)のもう1つのトイレがあります。

ちびっこ冒険広場:240m、レストハウス:350m、カラマツ広場:362m、マカバ広場:929mの看板があります。右側に階段があり、さらに上まで行けるようです。
この辺りから野生のにおいがするようになって、熊が出そうな感じでした。

「高丘森林公園」の山林で熊の目撃情報があり(令和7年10月20日、高丘霊園付近)、立入禁止になっていました。
野生の動物が生息しているにおいがすると思ったら、「高丘森林公園」の入口付近に野生の鹿(エゾシカ)がいました。鹿の糞みたいなのが、あちこちにあるなと思っていたら本当に野生の鹿だったという驚き。

金太郎の池の終わり(北側)で撮影した紅葉写真です。


望遠寄りで緑ヶ丘公園(金太郎の池)の紅葉、水鳥、鹿を撮影した写真
普段は、どこで撮影した写真か分かるように広角レンズでの撮影が多いですが、緑ヶ丘公園(金太郎の池)での写真撮影がとても楽しかったので、望遠寄りのレンズでも撮影しました。

















緑ヶ丘公園(金太郎の池)の住所・駐車場
■住所:北海道苫小牧市清水町3丁目1
開園・閉園時間等の詳細は公式サイトで確認してください。
☑https://midorigaoka-tomakomai.com/
■駐車場

無料の駐車場があります。


緑ヶ丘公園(金太郎の池)は、苫小牧市民の憩いの場として地元の方が多いですが、道外ナンバーの車も駐車場にありました。
とても素敵な公園で紅葉も綺麗でした。野鳥や水鳥など動植物を撮影しに行くのも楽しいと思いますよ。
以上です。